講演会
10月12日(日) 16:30~19:15
教育研修講演

膝関節温存治療の現状と未来
香川大学医学部 整形外科学 教授
石川 正和 先生
講演の内容
人生100年時代において、健康寿命の延伸は非常に重要な課題である。変形性膝関節症(膝OA)は歩行機能を低下させ、健康寿命に影響を及ぼす重要な疾患として認識されている。膝OAに対する人工膝関節置換術は良好な臨床成績が報告されており、コンピューター支援手術、ロボット手術なども普及してきた現在、最も効果が約束された手術と言っても過言ではない。一方、膝関節温存治療は、装具、ヒアルロン酸や自己多血小板血漿などの生物学的アプローチから、靱帯再建術、半月板縫合・再建術、骨軟骨柱移植術や自家培養軟骨移植術を含む軟骨修復術、骨切り術など、様々な治療が実施されている。しかし、初期OAは時に無症状かつ緩徐に進行するため、これらのアプローチが長期的に膝OA発症とその進行を抑制できるかどうかを判断することが難しい状況にある。現在進行形で、膝関節内の組織修復・再生および損傷・変性を惹起する環境を調整する新たな試みが行われており、日本においても今後、様々な選択肢が臨床の現場で提示されると予想する。本講演では、膝OA予防に向けた膝関節温存治療の現状と未来に関して紹介する。
Profile
| 1998年 | 徳島大学医学部医学科 卒業 |
|---|---|
| 2003年 | 神戸市地域結集型共同研究事業 特別研究員 |
| 2005年 | 国立大学法人広島大学非常勤職員 COE研究員 |
| 2009年 | 米国 Cardiovascular Research Institute, Case Western Reserve University (Cleveland, OH) Senior research associate |
| 2013年 | 広島大学病院 病院助教 |
| 2015年 | 広島大学大学院 助教 |
| 2019年 | 広島大学大学院 医系科学研究科 人工関節・生体材料学 寄附講座准教授 |
| 2022年 | 香川大学医学部 整形外科学 教授 |
現在に至る
| 日整会単位申請 |
|
|---|
お詫び
第51回JCOA研修会において日本整形外科学会の教育研修講演として単位取得ができるはずでしたが
香川県臨床整形外科医会(KCOA)の不手際により研修会の申請期日に間に合わず
単位取得ができなくなってしまいました。
学術講演1題、文化講演2題については予定通り講演会は開催されますが
単位取得ができません。
先生方には大変ご迷惑をおかけすることとなり、伏してお詫びを申し上げます。
文化講演①

美術は香川の土地を顕かにする
~瀬戸内国際芸術祭を巡って~
瀬戸内国際芸術祭 総合ディレクター
北川フラム 先生
講演の内容
鉄筋コンクリート、ガラスのカーテンウォール、空調付き高層ビルに代表される均質空間が世界を覆い、自然と人間が切り離されるようになりました。美術も白い高い壁(ホワイトキューヴ)のなかでの分析的なものになり、それが効果的な交換価値をもつようになりもてはやされています。
しかし、美術はもともと人間の身体が自然とどう関わるか?感じているか?から始まった自然と人間の関わり方の方法でした。その結果が作品となり展示されるようになって、本来のはたらきを失ってきました。
ホモサピエンスが南アメリカに到達する1万5000年程前までは、日本列島は人類にとって太平洋を前にしたフロンティアでした。そして瀬戸内の豊かで穏やかな海はその列島のコブクロのような揺籃の場で、古くからの歴史、貿易、産業の舞台でしたが、近代になり、海と島がもつ自由闊達さは失われ、地域力が減退していきました。これは国の情況そのものでした。
瀬戸内国際芸術祭はそんななかで、美術のもつ発見力、土地のもつ潜在力、気候、産業、文化に対する人と人を繋げる力をいかし、地域再生を目ざした地域づくりの総合的な施策として行われてきたものです。アーチストが着目した土地の特色は、地域住民、世界からやってくる数千人のサポーターとともに磨かれ、発展し、多くの人々を魅きつけてきました。ここでは海を渡り、個性ある島を歩くことが人間を元気づけ、リセットさせ、世界でも有数な楽しい、しかし人類はどこから来てどこへ行くかを考える旅だという評価を受け始めました。その内容と経過を具体的に話します。
Profile
1946年新潟県高田市(現上越市)生まれ。東京芸術大学美術学部卒業。アートフロントギャラリー代表。主なプロデュースとして、ガウディブームの下地をつくった「アントニオ・ガウディ展」(1978-79)、全国80校で開催された「子どものための版画展」(1980-82)、全国194ヶ所38万人を動員し、アパルトヘイトに反対する動きを草の根的に展開した「アパルトヘイト否!国際美術展」(1988-90)、米軍基地跡地を文化の街に変えた「ファーレ立川アートプロジェクト」(1994)等。地域づくりの実践として、「越後妻有アートトリエンナーレ」、「瀬戸内国際芸術祭」、「北アルプス国際芸術祭」、「奥能登国際芸術祭」、「内房総アートフェス」、「南飛騨アートディスカバリー」等の総合ディレクターをつとめる。フランス、ポーランド、オーストラリアから勲章を受勲。2016年紫綬褒章、2017年度朝日賞、2018年度文化功労者。2019年度イーハトーブ賞他を受賞。
文化講演②
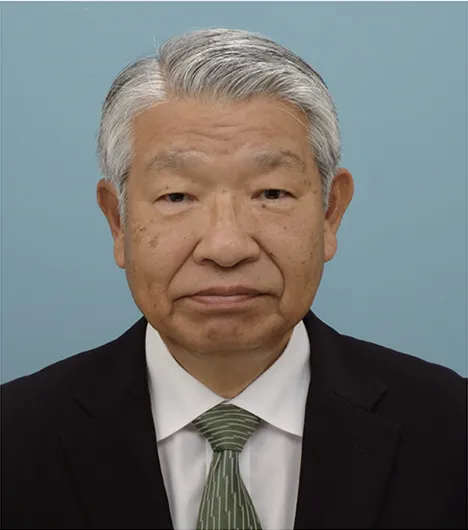
さぬきうどんの歴史と文化
さぬきうどん研究会 顧問
諏訪 輝生 先生
講演の内容
2011年10月、『香川県は「うどん県」に改名』と宣言しました。讃岐うどんが有名になったとは言え全国各地に多くの名産うどんがあるなかで、「香川県はうどん県」と名乗ることについてなぜ異論や異議が出なかったのでしょうか?
香川県民のうどん嗜好度、消費量、生産量、うどん店の数などは他県を圧倒して全国一位です。香川県内のうどん店は他県にはない形態の店(製麺所)があり、またうどんの食べ方にも独特のものがあります。
讃岐(香川県)では昔から干ばつと洪水が多発し米が不作の年が多く、その代用食として小麦を栽培してきました。江戸時代の百科事典などには讃岐の小麦の品質が日本一であったことや、飢饉で米がとれない時に庶民がうどんを食べたことが記録されています。また元禄時代の金比羅祭礼図屏風絵の参道には3店のうどん店が描かれています。讃岐のうどん食文化は江戸時代から昭和中期にわたり、農耕行事や年中行事などで食べる郷土料理として庶民の間に深く根付いた香川県独特の食文化です。
讃岐うどんは昭和時代の第1次、第2次から平成の第3次のブームを経て全国的に有名になり、その名は世界でも知られるようになりました。
ただ、どんなに全国や世界に広がろうとも、うどん県県民にとって『讃岐うどん』は、日常の極めて当たり前のうどん食文化そのものであることに変わりはないのです。
Profile
| 生年月日 | 1947年10月10日(開催日は78歳) |
|---|---|
| 現住所 | 香川県高松市(出身地も同じ) |
【学歴】
| 1966年 | 香川県立高松高等学校卒 |
|---|---|
| 1971年 | 日本国有鉄道中央鉄道学園大学課程業務科卒 |
【職歴】
| 1966年 | 日本国有鉄道四国支社入社 |
|---|---|
| 1987年 | 四国旅客鉄道(株)入社(総務・労務・人事担当) |
| 1995年 | 同 関連事業部事業課長兼営業課長 |
| 1998年 | (株)めりけんや代表取締役社長 |
| 2018年 | (公財)香川成人医学研究所専務理事(現在に至る) |
【うどん関係役職】
| 2007年 | 世界麺フェスタ2008 in さぬき実行委員会 幹事会幹事・麺分科会事務局長 |
|---|---|
| 2008年 | さぬきうどん振興協議会委員・事務局長 |
| 2012年 | さぬきうどん研究会副会長・総務部長 |
| 2014年 | 同 会長 |
| 2024年 | 同 顧問(現在に至る) |
【著書】
『七転び八起き さぬきうどんや奮戦記』
(2008年7月発刊 旭屋出版)
| 日整会単位申請 |
|
|---|
お詫び
第51回JCOA研修会において日本整形外科学会の教育研修講演として単位取得ができるはずでしたが
香川県臨床整形外科医会(KCOA)の不手際により研修会の申請期日に間に合わず
単位取得ができなくなってしまいました。
学術講演1題、文化講演2題については予定通り講演会は開催されますが
単位取得ができません。
先生方には大変ご迷惑をおかけすることとなり、伏してお詫びを申し上げます。